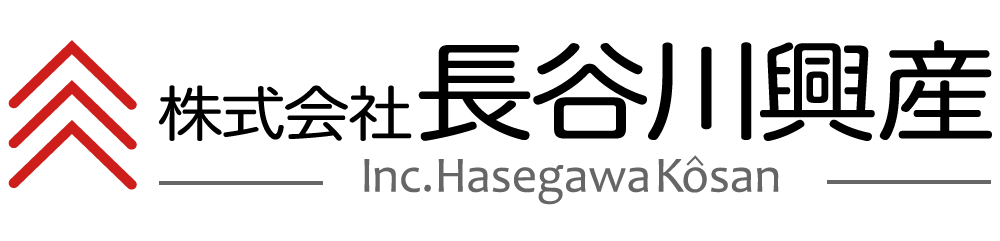人工木材は本当に腐らない?天然木との違いと正しいウッドデッキの選び方
2025.09.22

「人工木材は腐らない」というフレーズを目にしたことがある方は多いかもしれません。確かに、人工木材はメンテナンス性に優れ、腐敗に強いことで知られています。
しかし、この「腐らない」という言葉には、少なからず誤解が含まれています。現実には、人工木材にも劣化や損傷は起こり得ますし、万能ではありません。
人工木材が持つ本当の性能や限界を正しく理解することが、適切な木材選びには欠かせません。
さらに、科学的処理を施した高耐久な天然木も、今や人工木材と同等、あるいはそれ以上の性能を持つ時代になりました。
なかでも注目を集めているのが、「ノンケミカル・ノンビス工法・富山県産天然木」でつくられた次世代木材「The new Toyama Wood.」です。
この記事では、人工木材の実態とその誤解を明らかにしつつ、次世代天然木材の魅力についても深掘りしていきます。
人工木材とは何か?その定義と背景
人工木材とは、天然の木材に代わる素材として開発された「合成木材」のことです。主に樹脂と木粉を混ぜ合わせて作られ、ウッドデッキやフェンス、ベンチなど屋外空間を中心に広く使われています。
人工木材は、WPC(Wood Plastic Composite:木材・プラスチック複合材)とも呼ばれることがあり、以下のような構成を持っています。
●樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンなど)
木粉と混合して硬化させる基材。耐水性と成形性に優れる。
●木粉(天然木の細かい粉末)
外観の自然さや質感を高めるために添加される。
●添加剤(安定剤、着色剤など)
退色防止や耐候性向上のために加えられる補助成分。
このようにして生まれた人工木材は、天然木に比べて以下のような利点があります。
●メンテナンス性の高さ
塗装や防腐処理が不要で、手間がかからない。
●均質な品質
節や割れがなく、形状や寸法が安定している。
●耐候性
雨風に強く、屋外使用に適している。
こうした特性により、人工木材はウッドデッキなどの屋外構造物において広く採用されてきました。
背景には、天然木の劣化リスクや施工後のメンテナンス負担を回避したいというニーズがあります。人工木材はそうした課題に応える「便利な素材」として位置付けられてきたのです。
「腐らない」は正しいか?人工木材の耐久性の実態
一般的に「人工木材は腐らない」と言われますが、これは完全に正しいとは言えません。人工木材は確かに腐朽菌による腐敗には強いものの、別の形での劣化やトラブルが発生することもあります。
●カビ・藻の発生
木粉を含むため、表面に水分が溜まるとカビや藻が発生する可能性があります。
●色褪せ
紫外線や風雨により、徐々に色が褪せていきます。特に着色された製品は経年でムラが目立つことがあります。
●割れ・剥離
強い日差しや気温差にさらされ続けると、表面が割れたり剥がれたりすることがあります。
●高温変形
夏場の直射日光によって表面温度が上昇し、変形や膨張が起こることもあります。
これらの現象は「腐る」とは異なりますが、見た目の劣化や安全性の低下に直結する問題です。
また、人工木材は木材と違い、経年劣化によって部分的な修復が難しい点も見逃せません。破損した場合はパネル全体の交換が必要になることもあります。
つまり、「腐らない=劣化しない」という意味ではないのです。
耐腐朽性には優れていても、人工木材にも寿命はあり、設置環境によっては十分な注意が求められます。
メリットだけではない?人工木材の限界と注意点
人工木材はメンテナンスが容易で耐久性が高い一方で、いくつかの注意点や欠点も存在します。これらを理解したうえで使用することで、想定外のトラブルを避けることができます。
●高温時の膨張や反り
樹脂成分が熱により柔らかくなるため、夏場の直射日光下では膨張や反りが発生することがあります。特に広範囲に敷設されたウッドデッキでは、わずかな変形が全体の見た目や安全性に影響します。
●滑りやすさの問題
表面にカビや藻が生えると滑りやすくなります。水回りや日陰の多い場所では転倒リスクが高まる可能性があります。
●傷や変色が目立つ
均質な表面を持つため、ひとたび傷がつくと目立ちやすく、部分補修が難しいという欠点があります。
●リサイクルの難しさ
木粉と樹脂を混合して成形されているため、素材分離が困難です。廃棄時には産業廃棄物として処理されることが多く、環境負荷の懸念があります。
●天然木にはない質感の違和感
一見木材のように見えても、触ったときの感触や風合いに違和感を覚える方もいます。人工的な見た目や質感を嫌うユーザーには不向きです。
このように、人工木材は確かに扱いやすい素材ではありますが、「万能」というわけではありません。使用場所や目的を見極め、適材適所で活用することが求められます。
木材の腐敗はなぜ起こる?──天然木と人工木の腐朽メカニズム
木材が腐る主な原因は、腐朽菌と呼ばれる微生物の働きによるものです。特に褐色腐朽菌や白色腐朽菌は木材の主要成分であるセルロースやリグニンを分解し、木材の構造を弱くしていきます。
腐敗が起こる条件は以下の3つが揃ったときです。
●水分
木材含水率が20%を超えると、腐朽菌の活動が活発になります。
●酸素
密閉された環境では活動しにくく、空気との接触がある場所で腐朽しやすくなります。
●適温
腐朽菌は15〜30度の温度帯で最も活動が活発になります。
この3つの条件が同時に存在すると、木材は腐りやすくなります。
人工木材は樹脂を含んでいるため、腐朽菌が木粉に直接触れにくく、腐敗が進みにくいとされています。ただし、木粉自体が混入しているため、完全に腐敗リスクがゼロになるわけではありません。
一方、天然木は本来、水分を吸収しやすく通気性もあるため、未処理の状態では腐朽しやすい傾向にあります。
しかし、現代ではさまざまな「木材処理技術」によって、天然木でも高い耐腐朽性を実現することが可能です。
●加圧注入処理
木材の内部まで薬剤を加圧注入し、腐朽菌の侵入を防ぎます。
●熱処理(サーマルモディフィケーション)
高温で木材を処理し、含水率を極限まで低下させることで腐朽菌の活動を抑制します。
●乾燥処理
天然乾燥や人工乾燥によって、腐りにくい状態を長期的に維持します。
このように、木材の腐敗は「素材の問題」というよりも、「環境と処理技術」による影響が大きいのです。科学的に処理された天然木材であれば、人工木材と遜色ない、あるいはそれ以上の耐久性を発揮することもあります。
「腐らない木材」は人工だけじゃない?──天然木でも実現できる耐久性
天然木=腐るというイメージは過去のものになりつつあります。現代の木材処理技術の進化により、天然木でも高い耐久性を実現することが可能となりました。
以下に、天然木の耐腐朽性を高める主な処理技術を紹介します。
●熱処理(サーマルモディフィケーション)
高温の蒸気や無酸素状態で木材を加熱処理することで、内部の水分を除去し、腐朽菌の栄養源を絶ちます。寸法安定性が向上し、腐敗・反り・割れが起きにくくなります。
●加圧注入処理(ACQなど)
防腐・防蟻性能を持つ薬剤を木材内部にまで加圧注入します。住宅の土台などに使われる手法で、長期耐久性を確保することができます。
●高温乾燥処理(高周波・真空乾燥など)
木材の水分を極限まで抜くことで、腐敗しにくくなるとともに、収縮や膨張を防ぎます。加工後の寸法精度が非常に高いのが特徴です。
●天然由来の防腐処理
化学物質を使わず、柿渋やホウ酸など自然素材によって防腐処理を行う方法も注目されています。環境負荷を抑えたい現場で重宝されています。
これらの技術を駆使すれば、天然木であっても20年以上屋外で使用に耐える耐久性を持たせることが可能です。
特に、近年では「ノンケミカル処理」へのニーズが高まっており、環境や健康への影響を最小限に抑えた高耐久天然木材が多く開発されています。
その代表格が、富山県産スギを使った「The new Toyama Wood.」です。
高耐久天然木の実例:「The new Toyama Wood.」
「The new Toyama Wood.」は、富山県産のスギ材を原料に、水と熱だけを使って処理された、まったく新しいノンケミカル木材です。化学薬品を使用せずに高い耐久性と寸法安定性を実現した次世代の天然素材として注目されています。
●使用される木材:富山県産スギ100%
地元の資源を活用し、地域経済と森林保全にも貢献しています。
●処理方法:熱と水による独自の無薬剤処理
高温で芯まで処理することで、木材の内部から水分を徹底除去。これにより腐朽菌の活動が抑えられ、長期耐久性が確保されます。
●仕上がり:深いモカ色の美しい外観
コーヒー豆の焙煎に似た熱処理によって、自然で落ち着いた色合いを実現。木口まで着色されるため、塗装の必要もありません。
●用途:ウッドデッキ、外壁材、内装、建具など
高い耐水性と寸法安定性を備え、屋内外を問わず幅広い用途に対応しています。
なぜ腐りにくいのか?科学的な処理プロセスの説明
The new Toyama Wood.が腐りにくい理由は、その処理プロセスにあります。従来の天然木材とは一線を画す技術が使われています。
●芯まで熱を届ける熱処理技術
木材の芯までしっかり熱を伝えることで、内部の水分を極限まで除去します。水分がないため、腐朽菌は活動できません。
●寸法安定性の確保
熱処理によって木材の構造が安定し、膨張や収縮が起きにくくなります。これにより、反りや割れといった天然木の弱点を克服しています。
●無薬剤でもJIS基準をクリア
「褐色腐朽菌」による耐腐朽性試験では、質量減少率3%以内というJIS K 1517の基準を満たしており、高い実用性と信頼性を持ちます。
このように、The new Toyama Wood.は「腐らない木材」を天然素材で実現した、画期的な製品です。化学薬品を使わないため、施工環境や設置場所を選ばず、安全性にも優れています。
環境配慮・安全性も兼ね備える次世代木材
The new Toyama Wood.のもう一つの大きな特長は、地球環境と人への配慮が徹底されている点にあります。
●ノンケミカル処理
一切の化学物質や石油由来物質を使用せず、「水」と「熱」だけで処理されています。これにより、子どもやペットがいる家庭、公共施設や教育機関など、あらゆる場所に安心して使用できます。
●脱炭素・カーボンニュートラルに貢献
地元・富山県のスギを使用することで、輸送時のCO₂排出量を削減。さらに、木材自体が成長過程でCO₂を吸収しているため、使用することが環境保全活動にも直結します。
●SDGsとの親和性
12「つくる責任、つかう責任」や13「気候変動に具体的な対策を」など、複数のSDGs目標にも貢献可能な製品です。設計事務所や公共案件にも採用しやすいサステナブル建材と言えます。
●施工後の安全性
ノンビス工法によって、天面に金属部品が一切露出しません。素足で歩いてもケガの心配がなく、子どもや高齢者にも配慮された構造です。
●水はけ・ノンスリップ性能
表面には独特の波目模様が施されており、見た目の美しさだけでなく、滑り止め効果と水はけ性能を実現しています。安全性と快適性の両立が可能です。
このように、The new Toyama Wood.は素材・性能・環境配慮のすべてを高いレベルで兼ね備えた、次世代の天然木材です。公共施設や高齢者福祉施設、小学校や公園など、安全性と環境配慮が求められる場面に最適な選択肢となります。
人工木材 vs 高耐久天然木:選び方のポイント
木材を選ぶ際には、単に「腐らないかどうか」だけでなく、用途や設置環境、ライフサイクル全体を見据えた比較が必要です。ここでは、人工木材とThe new Toyama Wood.のような高耐久天然木の主な比較ポイントを整理します。
●設置環境との相性
湿気が多い場所や水回りには、寸法安定性の高い処理木材が有利。高温になる屋外では、人工木材の変形に注意が必要です。
●見た目・質感
人工木材は均質で見た目が安定している反面、天然木独自の風合いや経年変化は期待できません。一方、The new Toyama Wood.は天然木ならではの質感と、年を重ねるごとに深まる表情が魅力です。
●施工性とメンテナンス
ノンビス工法の天然木材は、施工が簡単で部分補修も容易です。人工木材は加工しやすい反面、破損時には交換範囲が広がることもあります。
●安全性
The new Toyama Wood.は化学物質を含まず、素足で歩いても安心。人工木材には樹脂由来の熱膨張や滑りやすさといったリスクもあります。
●価格とライフサイクルコスト
初期費用は人工木材の方が安い場合もありますが、メンテナンスや交換頻度、廃棄時のコストを含めると、長期的には天然木材が有利になるケースもあります。
このように、両者には明確な違いがあります。
人工木材は一定の条件下で非常に便利な素材ですが、自然な質感や環境配慮、安全性を重視するなら、高耐久な天然木材という選択肢も非常に有力です。
特にThe new Toyama Wood.は、天然木でありながら人工木材に勝るとも劣らない性能を持ち、多様なニーズに対応できる次世代型の素材です。住宅から商業施設、公共空間まで幅広く対応可能です。
まとめ

「人工木材は腐らない」というイメージは、一部では事実に近いものの、すべてを正確に表しているわけではありません。
人工木材は確かに耐腐朽性が高く、メンテナンスの手間も少ない優れた素材です。しかし、色褪せや高温による変形、滑りやすさなどの課題も存在します。さらに、廃棄時の環境負荷や再利用の難しさも見過ごせません。
一方で、天然木にも高度な処理技術によって「腐りにくい木材」が存在します。熱処理や加圧注入による加工を施すことで、天然素材でありながら高い耐久性と安全性を備える木材が実現されているのです。
とりわけ、富山県産スギを用いた「The new Toyama Wood.」は、水と熱だけで処理されたノンケミカル素材でありながら、JIS基準を満たす耐腐朽性、優れた寸法安定性、美しい見た目を兼ね備えています。
加えて、脱炭素やSDGsといった現代の環境課題にも応えるサステナブルな選択肢として、公共施設や商業施設でも導入しやすい素材となっています。
木材選びで最も大切なのは、「万能な素材」を求めるのではなく、「用途や環境に合った最適な素材」を選ぶことです。
●屋外での耐久性が最優先なら、処理された天然木が最適。
●意匠性や触感、安全性、環境配慮も重要なら、The new Toyama Wood.のような次世代素材が選ばれるべきです。
「腐らない木材」は存在しますが、それぞれに長所と短所があります。だからこそ、木材選びは表面的なキャッチコピーに惑わされず、性能・環境・美観・安全性といった多面的な視点から判断する必要があるのです。
本記事を通じて、人工木材の限界と、天然木材の可能性を再認識していただけたなら幸いです。
これからの木材選びには、科学技術と地域資源が融合した、持続可能な「新しい選択肢」が求められています。