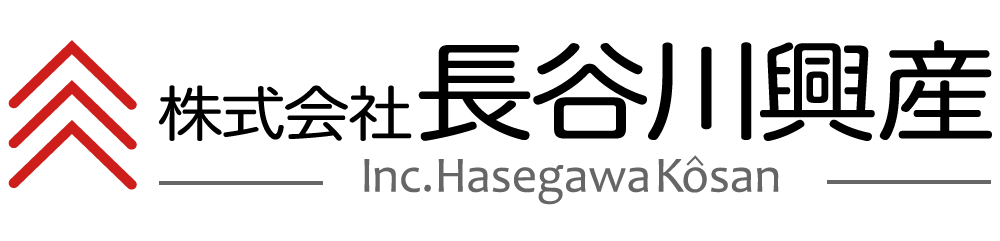木材はもう腐らない?最新ウッドデッキ技術で「天然木=不安」を解消!
2025.06.25

「天然木のウッドデッキは腐るから不安」と感じる人は少なくありません。実際、屋外に木材を使う際に多くの人が慎重になる理由は、腐食や劣化のリスクがあるからです。
しかし、「木材=腐る」という常識は、もはや過去のものになりつつあります。最近では、薬剤を使わずとも腐りにくく、長持ちして手入れも簡単な天然木材が登場しています。
その代表が、富山県産スギを使った「The new Toyama Wood.」。水と熱だけで処理されたこのノンケミカル木材は、天然素材の美しさを保ちながら、防腐性・耐久性・安全性を実現しています。
さらに、雨水の侵入を防ぐ「ノンビス工法」によって、構造面からも腐朽リスクを最小限に抑えられます。自然素材にこだわりたい住宅所有者や設計者にとって、画期的な選択肢です。
この記事では、こうした最新のウッドデッキ技術を科学と構造の視点から解説し、「木は腐る」という固定観念に疑問を抱くすべての方に、新しい選択肢をご紹介します。
腐朽のメカニズムを正しく知る:木材はなぜ腐るのか
天然木が腐る原因を正しく理解することが、防腐対策の第一歩です。腐朽は自然界の働きですが、技術でコントロールできます。
腐朽菌とは何か
木材を腐らせる主な原因は、「腐朽菌」と呼ばれる微生物です。これらは木材に含まれるセルロースやリグニンを栄養源として分解します。
●褐色腐朽菌
セルロースを分解し、木材を茶色くもろい状態にします。住宅の構造材に深刻な影響を与えます。
●白色腐朽菌
リグニンまで分解し、木材全体を白っぽく繊維状に劣化させます。
●軟腐朽菌
高湿度で活発になり、表面から内部に向かって木材を侵食します。
これらの菌は特定の温度や湿度の条件で活発になり、木の強度や見た目を大きく損ないます。
水分が鍵を握る:含水率と腐朽リスクの関係
腐朽菌が活動するには「水分」が不可欠です。木材の含水率が高くなるほど、菌の活動も活発になります。
●含水率が20%を超えると、腐朽菌の活動が促進されます
●30%を超えると、ほとんどの腐朽菌が繁殖可能になります
●18%以下に抑えれば、多くの腐朽菌は活動できません
つまり、防腐性を高めるには含水率のコントロールがもっとも効果的です。これが、ノンケミカル防腐技術の核心となります。
ノンケミカルで腐らない木材は可能か?
従来の防腐木材には、化学薬剤を加圧注入する方法が一般的でした。しかし近年、健康や環境への配慮から、薬剤を使わない処理方法に注目が集まっています。天然木の風合いを損なわず、安全性と耐久性を両立する新技術が求められています。
水と熱だけで木材は変わるのか
木材が腐る主な原因は水分です。この水分を取り除ければ、薬剤を使わずとも防腐性を高められます。その発想から生まれたのが、水と熱だけを使う処理技術です。
●高温の窯で芯まで加熱処理し、木材内部の水分を極限まで除去
→ 含水率が下がり、腐朽菌が活動できない環境になります
●木材組織に変化が起こり、湿気を吸いにくくなる
→ 吸湿性が抑えられ、寸法安定性が向上します
●薬剤不使用なので、安全性が高く、屋内外を問わず使える
→ 子どもやペットのいる場所にも安心です
このように、熱処理によって、薬剤なしでも腐らない木材を実現できます。
腐朽菌が生存できない状態をつくるには
腐朽菌の活動を止めるには、含水率を18%以下に保つことが重要です。水と熱で処理された木材は、以下のような特長を持ちます。
●含水率が10%前後まで下げられる
→ 腐朽菌がほとんど活動できない環境になります
●木の細胞構造が変化し、湿気を吸いにくくなる
→ 外部からの湿気にも強くなります
●芯まで均一に処理され、全体の品質が安定
→ 特定部分だけが劣化するリスクを大幅に減らせます
こうした技術により、天然木の風合いを活かしながら、薬剤に頼らず高い防腐性能を備えた木材が誕生しています。
富山県産スギの熱処理材が持つ防腐性能の実証
ノンケミカル処理の理論だけでなく、その効果が実証されていることも重要です。富山県産スギを使った「The new Toyama Wood.」は、実際の試験で高い防腐性能が確認されています。
JIS基準を満たす耐腐朽性の裏付け
木材の耐腐朽性は、日本工業規格「JIS K 1517」に基づいて評価されます。この試験では、木材の質量減少率が3%以内であれば、高い耐久性があるとされます。
●「The new Toyama Wood.」は、褐色腐朽菌による試験で質量減少率が3%未満
→ 薬剤を使わなくても、優れた防腐性能を示しました
●試験は信頼性の高い第三者機関が実施
→ 客観的なデータとして評価されています
この結果から、ノンケミカルでも腐らない木材が、理論上だけでなく現実の選択肢であることが証明されています。
芯まで均一な処理による腐朽リスクの最小化
木材の防腐性を高めるには、表面だけでなく内部まで均一に処理されていることが重要です。「The new Toyama Wood.」は、芯までしっかり熱処理されており、以下のような効果があります。
●内部まで均一な性質で、全体の耐久性が安定
→ 長期間にわたって高い性能を維持できます
●切断面や木口の追加処理が不要
→ 水の侵入による劣化を防げます
●内部まで美しいモカ色に染まり、見た目にも統一感
→ 景観との相性も良く、美しさを保てます
このように、芯まで処理された木材は、部分的な腐朽リスクを排除し、長寿命化に大きく貢献します。
ノンビス工法が腐食の原因を構造から断つ
木材の腐食は、素材だけでなく構造にも原因があります。ウッドデッキでは、天面に設けたビス穴が雨水の侵入口となり、内部から腐朽を引き起こすことがあります。そこで注目されているのが、天面にビスを一切使わない「ノンビス工法」です。
ビス穴がもたらす“見えない腐食”のリスク
これまでのウッドデッキでは、板材を固定するためにビスを使うのが一般的でしたが、このビス穴が腐食の原因になることがあります。
●ビス穴から雨水が入り込み、内部に湿気がこもる
→ 含水率が局所的に上がり、腐朽菌が繁殖しやすくなります
●ビス周辺に力が集中してひび割れが発生
→ そこから腐食が進む可能性があります
●表面が防腐処理されていても、ビス穴の処理が不十分だと効果が下がる
→ 部分的な劣化が構造全体に影響します
こうした構造上の弱点を解決するために、ノンビス工法が開発されました。
表面に一切の開口部を作らない設計とは
ノンビス工法では、天面にビスやネジを使わず、専用の金具で裏側から板材を固定します。これにより、表面に穴が一切ない、なめらかで美しいデッキが完成します。
●専用金具で裏から固定するため、雨水の侵入経路を遮断
→ 水分が染み込まず、腐朽リスクが下がります
●フラットな天面は、水たまりや汚れができにくく掃除も簡単
→ 清潔に保ちやすく、小さな子どもやペットにも安心です
●特許取得済みの設計で、強度と施工性も確保
→ 特許第7092376号を取得し、信頼性ある工法です
このように、ノンビス工法は素材だけでなく、構造からも腐食のリスクを減らす有効な手段です。
防腐薬剤に頼らない木材保護という選択肢
これまで、木材の防腐処理には薬剤の加圧注入が主流でした。しかし、環境や健康への影響を考慮し、薬剤を使わない新しい方法への関心が高まっています。熱処理された木材は、その有力な代替技術として注目されています。
薬剤処理木材との違いは何か
化学薬剤を使った木材とノンケミカル処理木材には、明確な違いがあります。以下のように整理できます。
●処理方法
薬剤処理材は木材に薬剤を浸透させるのに対し、ノンケミカル材は高温処理で水分と腐朽の要因を取り除きます
●安全性
薬剤処理材には残留薬剤があるため、子どもやペットとの接触には注意が必要です。ノンケミカル材は薬剤不使用のため、屋内外問わず安心して使えます
●環境負荷
ノンケミカル材は化学物質が流出せず、廃棄時も環境への影響が少ない
→ 持続可能な素材として高く評価されています
●メンテナンス性
薬剤処理材は再塗布が必要なことがありますが、ノンケミカル材はメンテナンスの手間が少なくて済みます
これらの点から、ノンケミカル木材は安全性と環境配慮を両立した素材として注目されています。
合成材では得られない「自然素材の防腐力」
合成木材は腐らないことが強みですが、天然木ならではの風合いや経年変化の美しさはありません。熱処理された天然木は、それらを兼ね備えた素材です。
●自然な木目や節を活かし、景観に馴染む
→ 天然素材ならではの温かみがあります
●加熱処理で深みのあるモカ色になり、色持ちも良い
→ 時間とともにシルバーグレイに変化する風合いも魅力です
●香りや手触りを残したまま高耐久性を実現
→ 住宅や商業施設など、幅広い用途で活躍します
このように、ノンケミカル天然木は、合成材や薬剤処理材にはない魅力と機能性を兼ね備えています。
腐らない天然木で築く、持続可能な木材利用の未来
「天然木=腐る」という考えを覆すノンケミカル木材は、単なる素材の進化にとどまりません。循環型社会の実現や、持続可能な資源活用にもつながる力を持っています。
ノンケミカル処理によって腐朽リスクを克服した天然木は、次のような価値を生み出します。
●地域資源の活用で地元経済を活性化
富山県産スギのような地場材を使うことで、森林資源を循環的に利用でき、林業や加工業への波及効果も期待できます
●化学薬剤を使わないことで環境への負荷を軽減
製造から廃棄まで薬剤を使わないため、土壌や河川を汚染するリスクがありません
●高い耐久性により長寿命化と資源節約を実現
20年以上の耐用年数があるため、交換や修繕の頻度が減り、ライフサイクル全体の資材消費が抑えられます
●安全性の高さで使用場所の幅が広がる
屋内外を問わず設置可能で、住宅や公共施設、高齢者施設など幅広いシーンで活躍します
腐らない天然木は、単に「長持ちする素材」ではなく、社会全体の持続可能性にも貢献できる存在です。
ノンビス工法のような構造技術と組み合わせれば、美しさ・機能・安全性のすべてを備えた空間づくりが可能になります。これは、設計者や施工者にとっても、より自由で魅力的な提案ができる新たな選択肢です。
自然素材の持つ美しさと実用性を両立し、同時に社会課題の解決にも寄与できる天然木ウッドデッキは、これからの暮らしや建築の「新しいスタンダード」となっていくでしょう。
まとめ

「天然木は腐る」「屋外には向かない」――そんな常識をくつがえす、ノンケミカルで高耐久な天然木ウッドデッキが登場しました。これは、木材利用の未来を大きく変える可能性を秘めています。
富山県産スギを水と熱だけで処理したこの木材は、腐朽菌が活動できない含水率を実現し、芯まで均一な処理で長寿命化を可能にしました。さらに、天面にビスを使わない「ノンビス工法」により、構造的な腐朽リスクも回避でき、安全性と美しさを両立しています。
薬剤に頼らず、自然の力と構造技術で防腐性能を高めたこの素材は、環境にやさしく、地域の資源を活かしながら、安心・安全で快適な空間を生み出します。