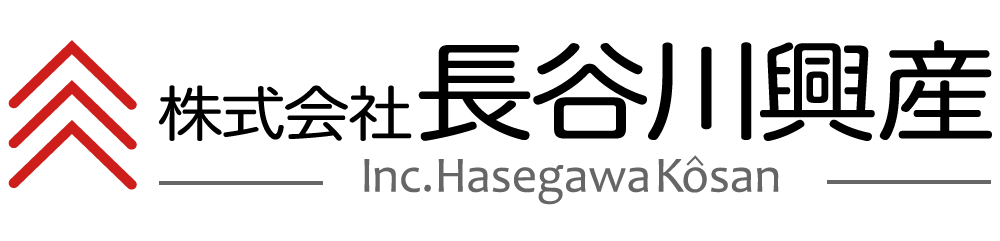ノンケミカルで20年耐久!富山県産スギ「The new Toyama Wood」の性能
2025.06.12

天然木のウッドデッキは、その自然な風合いや温もりから多くの人に選ばれています。中でも代表的な木材が「スギ」と「アカマツ」です。
スギやアカマツは古くから住宅や家具に使われてきた国産材であり、それぞれに特徴があります。しかし、耐久性や寸法安定性の面では、屋外で長く使用するには一定の課題も残されています。
耐久性や寸法安定性の課題をクリアし、屋外で20年の使用に耐えられるのが、富山県産スギを使用し、ノンケミカル処理によって性能を高めた「The new Toyama Wood」です。従来の天然木にあった弱点を克服し、美しさと耐久性を両立した新世代の木材として、公共施設を中心に導入が進んでいます。
この記事では、スギやアカマツとの比較を通じて「The new Toyama Wood」がいかに優れた木材かを解説します。天然木ならではの質感を残しつつ、環境や安全にも配慮されたこのウッドデッキの魅力を、ぜひご確認ください。
天然木ウッドデッキに使われる木材の基本比較
スギやアカマツといった代表的な天然木の特徴を比較し、それぞれの利点や課題を明らかにします。素材選びの基本を押さえることで、「The new Toyama Wood」の価値が際立ちます。
耐久性・耐腐朽性の違い
屋外に使用される木材は、雨風や紫外線にさらされるため、耐久性が重要です。腐朽菌やシロアリなどへの耐性は、素材選びの重要な判断基準となります。
スギ
日本各地で豊富に育ち、加工がしやすく軽量です。ただし、天然のままでは腐りやすく、屋外では数年で劣化することがあります。防腐剤による処理が必要です。
アカマツ
硬めで強度がありますが、ヤニが多く、腐朽にはやや弱い傾向があります。スギよりは耐久性がありますが、メンテナンスを怠ると劣化が進みます。
The new Toyama Wood
富山県産スギに水と熱のみで行う独自の熱処理を施し、腐りにくさを大幅に向上させた木材です。JIS K 1517の耐腐朽性基準もクリアしており、ACQ処理による補強も可能です。熱処置とACQ処理を組み合わせることで、20年以上の屋外使用にも耐える高い耐久性を実現しています。
割れやすさ・反りやすさの比較
木材は乾燥や湿気の影響で割れたり反ったりする性質があります。ウッドデッキとしての快適さを保つためには、割れや反りへの強さが求められます。
スギ
乾燥収縮が大きく、割れやすく反りやすい傾向があります。屋外にそのまま設置すると変形が進行しやすく、施工後のメンテナンスが欠かせません。
アカマツ
年輪が密で強度はありますが、含水率の変化に弱く、節が多い部分ではひび割れが生じることがあります。施工前の乾燥処理が重要です。
The new Toyama Wood
独自の熱処理によって木材内部の水分を極限まで抜いているため、割れや反りが起きにくく、非常に高い寸法安定性を備えています。芯まで処理することで含水率の変化による内部応力を抑え、長期的に安定した形状を保ちます。
寸法安定性の違い
木材が湿気を吸収・放出することで膨張や収縮を繰り返すと、床材やデッキが浮いたり、隙間が生じたりすることがあります。このような寸法変化への耐性も比較ポイントです。
スギ・アカマツ
両者ともに吸湿性が高く、周囲の環境に応じて寸法が変化しやすいという課題があります。乾燥処理をしっかり行っても、完全には抑えられません。
The new Toyama Wood
熱処理による科学変化で水分との結合力を弱め、湿気を吸収しにくい構造を実現しています。湿度変化による伸縮が極めて少なく、長期間にわたって安定した状態を保つことができます。
「The new Toyama Wood」の革新性と信頼性
化学薬品に頼らず、水と熱だけで実現した高耐久性と安全性。従来の天然木が抱えていた課題を克服した、新しい木材の革新技術を解説します。
ノンケミカル処理とは?―水と熱だけで実現する高耐久木材
一般的に木材の耐久性を高めるには、防腐剤や化学薬品の注入が必要とされてきました。しかし薬品注入などの処理は、人体や環境への影響が懸念されます。
「The new Toyama Wood」では、化学物質を一切使用せず水と熱だけで処理を行います。この技術によって、以下のような高性能を実現しています。
化学物質ゼロで安全性が高い
人体や動植物に有害な物質を含まないため、小さなお子様やペットがいるご家庭にも安心して使用できます。
環境に優しい処理方法
廃棄時にも環境への負荷が極めて少なく、リサイクルや土に還すことも可能なサステナブルな素材です。
腐朽菌やシロアリにも強い
熱処理によって木材内部の水分が抜けるため、菌や虫の繁殖環境がなくなり、自然な防腐・防蟻性を実現します。
このノンケミカル処理により、「The new Toyama Wood」は天然木の質感と安全性を兼ね備えた次世代の木材として注目されています。
芯まで処理することで得られる品質の均一性
木材処理では、表面だけでなく芯まで均一に処理されるかが重要なポイントです。
「The new Toyama Wood」では、以下の点で他の木材と明確に差別化されています。
芯まで熱が届く構造
特殊な窯を使用して木材全体に均等に熱を加えることで、芯まで水分を徹底的に除去します。含水率のばらつきがなく、施工後の反りやひび割れが生じにくくなります。
ACQ処理との併用でさらに強化可能
処理済みの木材にACQ(防腐防蟻用の水溶性薬剤)を加圧注入することで、芯まで高い耐久性能を持たせることも可能です。
全体が均一に美しく着色される
芯まで処理された木材は自然にモカ色に変化し、木口の塗装が不要です。経年変化しても色のばらつきが少なく、美観を保ちやすいのも特徴です。
芯までの処理が行き届いているため、どの部位でも同じ品質と性能が期待でき、長期的な安定使用に大きく貢献します。
寸法安定性を保ちながら実現する長期耐久―20年以上の屋外利用にも耐える
「The new Toyama Wood」は、寸法安定性に加え、20年以上の耐用年数を見据えた設計がなされています。
耐腐朽性試験をクリア
JIS規格に基づく試験で、質量減少率3%以内という厳しい基準を満たしており、腐敗への耐性が数値で証明されています。
長期使用を見据えた寸法安定性
湿度や気温の変化が大きい屋外環境でも、割れや反り、伸縮が起きにくく、20年以上使用しても安定した状態を維持できます。
実例にもとづく信頼性
すでに店舗や公共施設で導入されており、過酷な使用条件でも高い性能を発揮しています。施工後のメンテナンス頻度も少なく、長期コストを抑える点も大きな利点です。
「The new Toyama Wood」は、熱処理によって変形しにくい構造に変化しており、天然木としては異例の寸法安定性と長期耐久性を実現しています。
美観性と安全性を両立させた「ノンビス工法」
見た目の美しさと安全性を高めるために開発された独自工法。天面ビスのない滑らかな仕上がりと、使用者への安心感を両立する特徴を紹介します。
天面ビスなしで得られる見た目の美しさと安心感
従来のウッドデッキでは、板材を固定するために天面からビスを打ち込む工法が一般的でした。しかしこの方法では、以下のような課題がありました。
表面にビスの頭が露出し、美観が損なわれる
天面にビスが見えることで、木材本来の美しさが損なわれていました。
ビス周辺の割れやサビが発生しやすい
長期間の使用でビス穴から水分が入り、割れやサビによる劣化が進行しやすくなります。
素足で歩いた際にケガのリスクがある
ビスの頭が出っ張っていたり、緩んだりすると、裸足や靴下での歩行に危険が伴います。
「The new Toyama Wood」は、自社開発の特殊金具を使用したノンビス工法により、これらの問題をすべて解決しています。
天面にビスが一切出ない
表面は完全にフラットで、どこから見ても美しい仕上がりになります。木材の自然な風合いをそのまま楽しめます。
小さな子どもがいても安心して使える
ビスが露出していないため、素足で歩いても安全です。保育施設や福祉施設など、安全性が求められる空間にも最適です。
高級感ある空間演出が可能
デッキ全体がスムーズな平面で構成されており、住宅の庭や商業施設のテラスに自然に溶け込む高級感を演出できます。
隙間がない構造で小物落下や水はけトラブルを防止
通常のウッドデッキでは、板と板の間に隙間を空けることが一般的です。これは水はけのための処置ですが、以下のようなデメリットもあります。
小物やコインが隙間に落ちる
店舗などでは商品や部品が隙間に落ちると、拾いにくく衛生的にも問題になります。
小さなお子様の足が引っかかる
隙間に足がはまるリスクがあり、安全面での配慮が必要です。
ゴミや落ち葉が溜まりやすい
隙間にゴミが挟まり、掃除が大変になるだけでなく、見た目も損ないます。
「The new Toyama Wood」は板材の間に隙間がない構造を採用しています。板材に隙間を作らないことで以下のようなメリットがあります。
コインや小物が落ちない
販売店舗や展示場など、小物を扱う空間でも安心して利用できます。
清掃がしやすく美観を保てる
ウッドデッキの下の空間にゴミが溜まりにくく、掃除も簡単です。清潔な環境を保ちたい飲食店や公共施設にも適しています。
水はけ性能も確保
波目のノンスリップ加工により、表面に水が溜まりにくく、滑りにくい構造です。安全性と機能性を両立しています。
このように、「ノンビス工法」と「隙間なし構造」の組み合わせは、美しさと安全性、高いメンテナンス性を実現します。
経年変化を楽しめる美しい色合い
「The new Toyama Wood」は、その美しい色合いも大きな魅力のひとつです。天然木ならではの経年変化を楽しむことができ、時間とともに深まる美観が多くのユーザーを惹きつけています。
施工直後のモカ色の落ち着いた風合い
熱処理により、木材は芯まで深く色づき、美しいモカブラウンに仕上がります。これは、コーヒー豆を焙煎するようにじっくりと熱を加えることで生まれる自然な色です。
経年によるシルバーグレーへの変化
紫外線や風雨に晒されることで、表面は徐々にシルバーグレーに変化します。これは天然木にしか表現できない、風格のある美しさです。
塗装不要で自然な風合いを維持
芯まで着色されているため、木口部分の塗り直しは不要です。塗装をしなくても見た目が整い、メンテナンスの手間を大幅に軽減できます。
こうした経年変化の美しさは、樹脂製や人工木材では決して再現できない天然木の大きな特長です。
利用シーン別に見る「The new Toyama Wood」の実力
住宅、店舗、公共施設など、幅広い用途に対応可能な「The new Toyama Wood」。実際の利用シーンに基づいた具体的な活用方法を紹介します。
一般住宅(庭・ベランダ)での活用
住宅の庭やベランダは、「The new Toyama Wood」の性能とデザイン性をもっとも身近に実感できる場所です。
ベランピングやBBQに最適
平坦でフラットなノンビス工法のデッキは、テーブルやチェアの設置がしやすく、快適なアウトドア空間をつくれます。家族や友人との食事、子どもの遊び場としても重宝します。
安全性が高く、子どもやペットにも安心
天面にビスがないため、素足で歩いても安全です。滑りにくい波目加工により、走り回っても転倒リスクを軽減できます。
日々の手入れがしやすい
隙間がない構造でゴミが溜まりにくく、掃除の手間も最小限です。水洗いだけで清潔な状態を維持できます。
住宅における「The new Toyama Wood」は、快適な暮らしと安心な生活空間を両立します。
店舗・商業施設・遊歩道など公共空間での活用
「The new Toyama Wood」は、住宅だけでなく、商業施設や公共空間でもその実力を発揮しています。
店舗テラスでの景観づくり
飲食店やカフェのテラスに使用すれば、木の温もりが来客を迎え、空間全体の印象が上質になります。経年変化も味わいとして活かせます。
遊歩道や園庭に適した安全性
ノンスリップ加工が施されており、雨の日でも滑りにくい構造です。公共施設や公園、保育施設などでも安全に利用できます。
メンテナンス性に優れる
フラット構造と簡易な施工方法により、部材単位での補修が可能です。人通りが多く、摩耗が激しい場所でも、長期使用に耐えられます。
このように、「The new Toyama Wood」は住宅から公共空間まで、さまざまな利用シーンに柔軟に対応できる多用途性を持っています。
地球環境と地域社会への貢献
富山県産スギを100%使用し、地域資源の活用とカーボンニュートラルを実現。環境への配慮と地域社会への貢献という付加価値を解説します。
富山県産スギ100%使用の意味と意義
「The new Toyama Wood」は、地元・富山県で育まれたスギを100%使用しています。木材としての品質だけでなく、地域経済や環境保全への貢献という大きな付加価値も持ちます。
地域資源の有効活用
富山県産のスギは、日本海側特有の厳しい気候で育つため、強くしなやかな性質を持っています。富山県産スギを木材として活用することで、地域林業の活性化につながります。
輸送エネルギー削減によるCO₂削減
地産地消により、遠方からの輸送エネルギーを抑えることができ、二酸化炭素の排出量削減にも貢献します。
地域の信頼とブランド構築
地元資源を積極的に活用する企業姿勢は、地域住民や行政からの信頼を高め、ブランド力の向上にも貢献します。
地域密着型の素材選びは、単なる木材の選定にとどまらず、持続可能な社会の形成にもつながります。
脱炭素・カーボンニュートラルを目指す企業姿勢
「The new Toyama Wood」は、次世代の建材として、カーボンニュートラルやSDGsに即した製品設計となっています。
ノンケミカル処理による環境負荷の軽減
化学物質を一切使わない処理方法により、製造から廃棄まで環境への負荷を最小限に抑えています。
熱処理による炭素固定
木材を高温で処理することにより、炭素の固定効果が高まり、長期間にわたって炭素を大気中に戻さない働きがあります。
SDGsの複数目標に貢献
目標12(つくる責任 つかう責任)、目標13(気候変動に具体的な対策を)、目標15(陸の豊かさも守ろう)など、多角的な貢献が可能です。
これらの取り組みを通じて、「The new Toyama Wood」は単なる建材ではなく、環境と社会に調和する未来志向の選択肢として注目されています。
なぜ今、「The new Toyama Wood」を選ぶべきか
「The new Toyama Wood」が選ばれる理由を、耐久性、施工性、提案力といった実務的な視点から整理しました。
天然木デッキの常識を変える「新しい基準」
天然木は「腐りやすい」「割れやすい」「手入れが大変」といったイメージを持たれがちです。しかし、「The new Toyama Wood」はその常識を根本から覆します。
化学物質ゼロでも腐らない木材
特殊な熱処理により、防腐剤に頼らなくても腐りにくい構造を実現しました。環境と健康に優しい安心の木材です。
割れや反りに強く、メンテナンスも簡単
水分変化に強く、施工後の変形が少ないため、手入れの手間が大幅に削減されます。住宅・商業施設問わず長期的に安定使用が可能です。
美しい経年変化で風格が増す
天然木ならではの味わいある色合いの変化を楽しむことができ、住まいや空間に深みを与えます。
「The new Toyama Wood」は、まさに天然木ウッドデッキの“新しいスタンダード”です。
設計者・施工者にとっての導入メリット
建築関連の事業者様にとっても、「The new Toyama Wood」は魅力的な素材です。性能だけでなく、施工性や提案力の強化にもつながります。
工期短縮・施工性の高さ
ノンビス工法により、デッキの施工は板材と金具をつなぐだけ。短時間で設置でき、現場作業の効率化に貢献します。
補修の容易さ
デッキ表面は1枚単位で取り外し可能なため、破損時の補修もスピーディー。部材交換のみで済み、コストも抑えられます。
提案力の差別化
天然木でありながら高耐久、ノンケミカル、美観性を備えた「The new Toyama Wood」は、他社と差がつく提案材料になります。
住宅・公共施設・商業施設など、あらゆるプロジェクトで「The new Toyama Wood」は価値ある選択肢となるはずです。
「天然木はすぐ腐る」はもう古い
「天然木=すぐ腐る」というイメージは、すでに過去のものです。
最新の熱処理技術で防腐剤不要でも高耐久
木材の中から徹底的に水分を抜くことで、腐朽菌や虫が繁殖しにくい環境を作ります。化学処理に頼らずに耐久性を確保しています。
寸法安定性に優れ、施工後も変形しにくい
木材の弱点とされていた“動きやすさ”を科学的に克服し、屋外でも安定した性能を発揮します。
ノンケミカルの安心感がさらに魅力を高める
人体やペット、自然環境への影響を考慮しながらも、高い性能を誇る素材は、次世代の建材として最適です。
まとめ

天然木ウッドデッキに求められる「耐久性」「美観」「安全性」「環境配慮」をすべて高い水準で満たす「The new Toyama Wood」。
●スギやアカマツを凌駕する寸法安定性と長期耐久性
●ノンケミカルでも腐りにくく、割れにくい次世代木材
●フラットな美しさと高い安全性を両立するノンビス工法
●富山県産材を活用した地域循環型の環境建材
●一般住宅から公共施設まで対応可能な施工性と補修性
「The new Toyama Wood」は、これからのウッドデッキ選びにおいて、新たなスタンダードとなる素材です。